こんにちは!
神社やお寺など神社仏閣、歴史が大好きな桜木です!
神社やお寺などが大好きな僕にとっては、【京都】は、本当に楽しい場所です。
かつて平安京という大きな都市だった京都は、日本の中心であり、神社やお寺が数多く残っている歴史的にも、素敵な場所です。
創建当時のものが、今の時代(令和時代)でも残っているものもありまして、観光地としては、最高の場所だと思っています。
山梨にいたころからも、京都は、何度か旅行で行ったこともありまして、修学旅行でも行きました。
修学旅行は中学生のときでしたが、当時は、まだ歴史への興味が今ほどなかったということと、そもそも修学旅行のように学校で泊まりがけで、どこかに行くというのが大嫌いだったので、あまり楽しかったという思い出がありませんでした。
京都が楽しい、おもしろい、また行きたいと思うようになったのは、大人になってからで、1人旅を初めてしたのが、実は【京都】だったんです。
有給を取って、3連休にして、【1泊2日】で短かったんですが、楽しくて、また来ようと思いました。
そのあとは、パートナーの彼と山梨から京都まで、遊びに行ったこともありまして、京都に旅行するごとに、また来たい、楽しいと思うようになりました。
僕は、今でも団体旅行とか団体行動みたいなことが、あまり好きではなく、個人とかパートナーの彼と2人だけとか、少ない人数での旅行とかが好きです。
パートナーの彼と2人であれば、好きなところとか、行きたい場所だけ行くことができますし、お互いに、行ってみたい場所も合うので、どこに旅行しても楽しい旅行ができます。
そして、今回の記事では、京都のなかでも、かつて平安京という大都市があった時代の正庁だった【平安神宮】について、ご紹介していきますね!
平安神宮とは、いったいどんなところなの?
京都府京都市左京区にある神社で、明治時代に作られた日本の神社のなかでは、比較的新しい神社となっています。
平安神宮が作られたのは、1895年(明治28年)に、【平安遷都1100年】を記念して作られた神社です。
そのころの京都というのは、幕末の混乱や明治維新による東京奠都(読み:とうきょうてんと、意味:江戸という名前を東京に変えて、首都を東京に定めるということ)などによって、京都の政治的、経済的首都機能が低下していた時代です。
幕末の混乱は、鉄砲焼け(読み:てっぽうやけ)と呼ばれる京都内で起きた戦いによって、京都の町の中心部で建物が、かなり消失してしまいました。
上記のような状態となってしまった京都ですが、市民が立ち上がって、かつての元気だった京都を取り戻したいという意気込みによって、京都のインフラであったり、学校設立であったり、京都の復興をがんばったおかげで、近代都市へと変化していきました。
その後、平安遷都1100年の記念と、第4回内国勧業博覧会(京都開催)にともないまして、市民から、京都の始祖である桓武天皇の御霊をまつる神社を作りたいと要望があり、この平安神宮を作ったそうです。
最初の御祭神は、【桓武天皇】のみでしたが、皇紀2600年(昭和15年、西暦:1940年)を記念して、平安京最後の天皇である【孝明天皇】も御祭神となりました。
(※皇紀2600年というのは、戦前まで日本で使われていた日本独自の暦で、皇紀元年は、日本の初代天皇である「神武天皇」が奈良県の橿原宮(現在の橿原神宮)で即位した年で、別の言い方をすれば、日本誕生(初代天皇即位)から数えた年です。)
ちなみに、今年(2025年)は、皇紀2685年で、今でも、この皇紀という数え方は、なくなったわけではないですが、一般的には使われていないだけです。
そして、平安神宮が建てられている、この場所は、かつて、平安京(京都の大都市)があったときの、大内裏の【正庁】であった【朝堂院】があった場所です。
当時よりは小さく作られていまして、当時の大きさの8分の5のサイズで、作られていますが、鮮やかな朱色など当時の建物と同じように再建されています。
平安神宮の見どころは、いっぱい!
平安神宮は、広い敷地にある神社ですので、見どころが多くあります。
その見どころである建物は、ほとんどが、【国の重要文化財】であったり、【国の登録有形文化財】であったりと、とても重要な文化財にも、なっています。
創建されたときに、作られた建物もありますが、創建されてから、しばらくしてから(昭和15年、皇紀2600年という記念のとき)作られた建物もあります。
・大鳥居
西暦1928年(昭和3年)のときに、昭和天皇の御大典(読み:ごたいてん、意味:天皇の即位の儀式のこと)が京都で行なわれたのですが、この後大典を記念して、翌年にできた大きな鳥居です。
作られた当時(昭和4年、西暦1929年)では、この鳥居は日本一大きな鳥居だったそうです。
現在は、この鳥居がある場所の公園(名前:岡崎公園)のシンボルになっていまして、国の指定文化財にも登録されています。
今でも、大きい鳥居なので、近くで見ますと、かなり迫力がある鳥居となっています。
・応天門
応天門(読み:おうてんもん)は、平安京の時代の大内裏の正庁である「朝堂院」の【南面正門】のことです。
神社の入口に建っていまして、二層の楼門となっていまして、朱色で塗られた建物です。
第4回内国勧業博覧会のモニュメントにもなったそうでして、明治28年(西暦1895年)に作られた建物です。
この建物は、重要文化財に登録をされています。
・大極殿
大極殿(読み:だいごくでん)は、応天門の北であり、本殿の南側に位置する主要な社殿のことです。
正面の長さは、なんと【30メートル】もありまして、かなり大きな建物となっていまして、入母屋造の屋根は、碧瓦(読み:へきが)を葺いていまして(読み:ふいていまして)、棟の両端には金色の鴟尾(読み:しび、意味:宮殿などの両端についている鳥の尾の形の飾りのこと)がついています。
この大極殿の前にある庭には、「左近の桜」「右近の橘(読み:たちばな、白い花のこと)」というものがあります。
かつて、平安京のときは、この大極殿は、重要な役割となっていまして、即位であったり、朝賀(読み:ちょうが、意味:元日に天皇が大極殿で群臣の祝賀を受ける儀式のこと)であったりと、重要な儀式を行なう場所でした。
・神苑
神苑(読み:しんえん)は、平安神宮の社殿を囲うように配置された庭園のことです。
その庭園の面積は、なんと【33,000平方メートル】というかなり広大な庭園になっています。
その神苑には、南エリア・西エリア・中エリア・東エリアの4か所にわかれていまして、それぞれのエリアでは、まったく異なった庭園となっています。
四季折々の風景を楽しめるように、それぞれで異なった庭園にしています。
南神苑(南エリア):平安時代の庭園のようになっていまして、「野筋(読み:のすじ、意味:野の道になぞって作った庭の道のこと)」や「遣水(読み:やりみず、意味:庭園の水路のこと)」などの様式でできている庭園となっています。
西神苑(西エリア):白虎池(読み:びゃっこいけ)を中心に、約200種2000株の花菖蒲(読み:はなしょうぶ)が咲く庭園となっています。
6月に見頃になる花となっていますので、梅雨の時期ですが、きれいな花を咲かせます。
中神苑(中エリア):蒼龍池(読み:そうりゅういけ)があり、「臥龍橋(読み:がりゅうきょう)」という飛び石が置かれていたり、睡蓮(読み:すいれん)などの花が咲いていたりする庭園です。
睡蓮は、夏ごろに咲く花ですので、西神苑の次の時期に、きれいな花を咲かせます。
東神苑(東エリア):神苑のなかで、一番大きな庭園で、「泰平閣(橋殿)(読み:たいへいかく)」や「尚美館(貴賓館)(読み:しょうびかん)」によってきれいな景色になっている庭園です。
とてもきれい!四季折々の景色
先ほど、見どころの章でも記載しましたが、平安神宮は、四季ごとに雰囲気が変わる神社となっていまして、季節ごとに違った景色を楽しむことができます。
まずは、【春】ですが、春といえば、【桜】ですよね。
平安神宮でも、桜の木があり、ピンク色のきれいな桜がこの時期になると、咲いていますので、桜の色と、平安神宮の建物とのコラボレーションは、とてもきれいです。
次に、【夏】ですが、夏の時期は、常緑樹の色鮮やかな緑色であったり、睡蓮の花などが咲いたりする時期で、とても、自然豊かな季節となっています。
夏は暑いですが、睡蓮は池に咲いていますので、涼し気な気持ちにもなれます。
それから、【秋】ですが、秋の時期は、なんといっても【紅葉】ですよね。
平安神宮のなかの木が、鮮やかな紅葉の色をしまして、とてもきれいです。
この紅葉の時期を迎えると、秋がやってきたという感じがします。
そして最後が【冬】ですが、この時期は、草花は、咲いていなくて、【雪】が魅力的となります。
平安神宮の建物が、雪景色となりますと、とても美しい姿をします。
冬は寒いですが、この美しい姿は、この時期でしか見れませんので、冬の時期もとてもおすすめです。
アクセス
住所:京都府京都市左京区岡崎西天王町97
駐車場:なし(近隣に、有料の京都市営岡崎公園駐車場というのがありますので、車で行かれる方は、こちらの駐車場を利用してください。)
最寄りインター:名神高速道路 / 京都東インター(このインターから車で約20分です。)
最寄りバス:JR「京都駅」または、阪急「河原町駅」
京都駅からは、市バスに乗り「岡崎公園 美術館・平安神宮前」で降りて、そこから歩いて5分(京都駅からの所要時間は、全体で約30分)
河原町駅からは、市バスに乗り「岡崎公園 美術館・平安神宮前」で降りて、そこから歩いて5分(河原町駅からの所要時間は、全体で約20分)
最寄り駅:地下鉄東西線「東山駅」または、京阪鴨東線「三条駅」または「神宮丸太町駅」
東山駅:駅の1番出口より徒歩10分
三条駅 or 神宮丸太町駅:駅の出口から徒歩15分
まとめ
今回は、京都市左京区にある【平安神宮】について、ご紹介してきました。
神社自体は、明治時代に作られた比較的新しい神社ですが、歴史を考えると1000年以上前の平安京の時代にあった建物の再建ですので、とても感慨深いですよね。
京都には、このような歴史のある建物が、数多くあり、それぞれで、いろんな歴史がありますので、それを知ることで日本の歴史も、楽しみながら勉強することができます。
ぜひ、みなさんも、京都に観光に来たときには、こちらの平安神宮を観光してみてはいかがでしょうか?
移住や、田舎暮らしはいかがでしょうか?
![]() 移住物件や田舎暮らし物件をお探しの方☚クリック
移住物件や田舎暮らし物件をお探しの方☚クリック
今日もありがとうございました。
皆さまにとって幸せな1日でありますように
その他の「田舎暮らし、リゾート」関連物件をご紹介
***********information***********
【別荘、田舎暮らし物件の不動産購入】のご相談はこちらへ
ご相談は、日本マウントホームページの問い合わせフォームからどうぞ!
売却のご相談![]() も承りますのでお気軽にお寄せ下さい!
も承りますのでお気軽にお寄せ下さい!
本社と現地スタッフのネットワークでいち早く対応します
【日本マウント】田舎暮らし中古住宅専門の不動産会社です
東京都品川区平塚2-5-8五反田ミカドビル3F
営業時間 > 月~金 9:00~18:00 / 土・日・祝日 9:00~18:00
電話 > TEL:03-6451-3960
★公式サイト:https://resort-estate.com/
★全国の物件なら「いなかも家探し」:https://resort-bukken.com/
★物件売却のご相談(無料):https://resort-estate.com/baikyaku
日本マウント公式instagram
別荘地での暮らし・地方移住に役立つ情報を
日々発信中!
https://www.instagram.com/nihonmount/
【不動産会社様へ】無料で物件掲載、反響が直に届くサービスの紹介
★無料で物件掲載について:https://resort-bukken.com/keisai














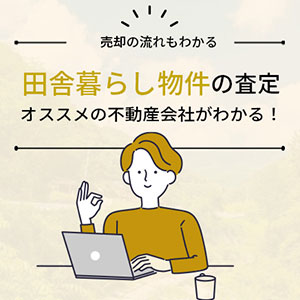
コメント